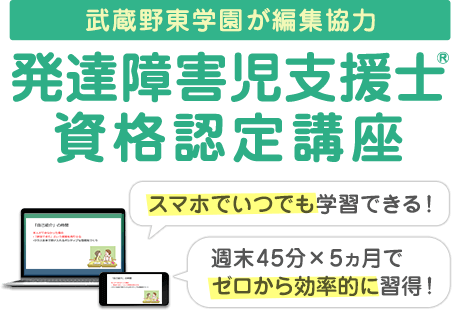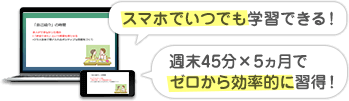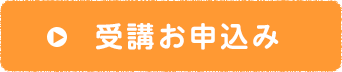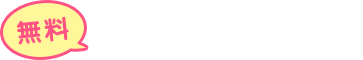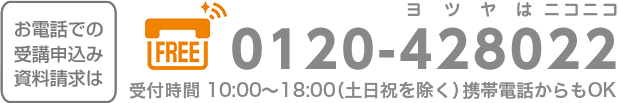発達が気になる子どもたちの支援にあたっている指導者の皆様へ


四谷学院の発達障害支援
2つの認定資格
発達障害児支援士資格認定講座

発達障害についての基本的な知識や具体的なアプローチ法を学びます。豊富な事例を通して「本当に効果があった」と認められた支援のノウハウを身につけていくことができます。
- 対象
-
どなたでも。
初めて発達障害について学ぶ方からすでに現場で活躍されている方まで、幅広く学んでいただくことができます。
発達障害児専門支援士資格認定講座

保護者や指導者から悩みの多い「ことば」の支援と、心身の発達の土台となる「運動」発達についての理解を深めていきます。2つの分野の専門性を高める中で、子ども個人の発達を促すためのアプローチや保護者対応のスキルを磨くことができます。
- 対象
- 「発達障害児支援士有資格者」または「発達障害児支援士資格取得見込み者」
- ことば
- 第1部:ことばの発達
- 第2部:ケーススタディ
- ことばが出ない
- 会話ができない
- 指示通りに動けない など
- 第3部:ことばを育てる関わり
- 運動
- 第1部:運動の発達
- 第2部:ケーススタディ
- 姿勢が悪い
- 落ち着きがない
- 手先が不器用 など
- 第3部:運動と生活の関わり
- 指導の心得
- 身辺自立
- 特性への対応
- ソーシャルスキル
- 問題行動への対応
資格取得までの学習モデル
発達障害児支援士+専門支援士の資格認定講座をセットで受講した場合


|
「支援士+専門支援士」 資格認定講座セット受講 |
発達障害児支援士 資格認定講座 |
(参考) 発達障害児専門支援士 資格認定講座※1 |
|
|---|---|---|---|
| 受講料 | 198,000円 (税込 217,800円) ※受験料を含む |
99,800円 (税込 109,780円) ※受験料を含む |
148,000円 (税込 162,800円) ※受験料を含む |
| 受講期間 | 2年間 | 1年間 | 1年間 |
| 標準学習期間 |
支援士:6ヵ月 専門支援士:6ヵ月 |
6ヵ月 | 6ヵ月 |
| 認定試験 | 受講期間中に受験可能 | 受講期間中に受験可能 | 受講期間中に受験可能 |
| 取得できる資格 |
発達障害児支援士 発達障害児専門支援士 |
発達障害児支援士 | 発達障害児専門支援士 |
![]()
※1 発達障害児専門支援士資格認定講座は、「発達障害児支援士講座資格取得見込みの方」または「発達障害児支援士資格取得済の方」のみお申込みいただけます。お申込みはこちら。
発達障害児専門支援士
受講体験記
 さんのご紹介
さんのご紹介
| 発達支援のご経験 | 児童発達支援事業所スタッフ |
|---|---|
| 経験年数 | 4-5年 |
受講前はどんなことに悩んでいましたか?
療育現場で受け持っているお子さんで、年少さんのお子さんがいらっしゃるんですけど、発語がほとんどないことと、それに代わる身振りとか手振りとか、そういう表出がほとんどなくって、そういうお子さんに対して何をきっかけに言葉のアプローチをしたらいいかっていうのを悩んでいたことがまず1つです。
もう1つは年中さんのお子さんで、言葉はすごく巧みに出るんですけれども、全てが一方的で、指導員や親の言葉が全く入らないというか、要求が叶えられないと怒ってしまったり、かんしゃくを起こしてしまったりというお子さんがいて、特にその2人のお子さんについては言葉(の支援法)について悩んでいました。
それと、保護者の方がやっぱり望まれることがすごく高いと言いますか、息子さんの発達段階に合ってないなっていうぐらいの高い要求をされるお母さんが多かったので、そこもちょっと悩んでるところではありました。
続きを読む
どんなことを学びたいと思っていましたか?
困り感が自分にもある時は、参考書を読んだり、周りのスタッフに聞いたりして知識をつけることはできるし、関わっているお子さんや今まで関わってきたお子さんの中での経験っていうのもあるんですけど、知識と経験が結構繋がらないというか、頭でわかってるけど、目の前のお子さんにそれを適用しても全然その通り行かないとか、思う通りに行かないとか、そういうことも多かったので、そこを繋げる何かアイテムが欲しいなっていうのをすごく思っていて。こちらの講座でそういう現場で使えるようなアイディアとか考え方を学べるっていうのが「あ、はやく見てみたい!」と思ったきっかけになりました。
最も印象に残っているテーマを教えてください
印象に残ってるのは、「子どもが言葉を使う必要性を感じていないこともある」っていう言葉です。言葉を使うことで状況が変わるということを経験することで、言葉を使ってみようと思わせる、という内容が、まず1つ目心に残ったかなと思います。2つ目は、三項関係が成立してこそ共同注視による言葉の獲得に繋がる、という内容のところです。
1つ目の「言葉を使う必要性を感じるかどうか」ということについては、先ほど1つ目の質問の時に話した年少さんのお子さんなんかだったら、最近少し言葉が出るんですけど、出る言葉と出ない言葉があったり、もしくは出るときと出ないときがあったり、なんでなのかなっていうのはすごく考えてたんですけど、「あ、なるほどこの時は必要だと感じてたんだな」とか「全く必要だと感じていなかったんだな」っていうところに気づくことができたので、特に印象に残っています。気づいてからは、その言葉が必要だなって感じられるように環境設定をするなど、心がけています。
また、2つ目の三項関係のところについては、クレーン現象が出るお子さんに対して、三項関係を意識して関わろうという風にはもともと思っていたんですけど、それが言葉の獲得の基礎だっていう認識が強くなかったので、それを意識することで、発語を直接促す声かけじゃなくても、共感性を高める声かけをするだけでも言葉の発達の基礎になるんだな、っていうことに気づくことができたので、印象に残っています。
どのように学習を進められましたか?
私は仕事が休みの日を中心に家事の合間にスマートフォンで受講しました。テキストはプリントアウトしたもの(ワークブック)を使っていました。(ワークブックは)絶対いるなっていうふうに思います。というのも、動画を見てインプットするだけじゃなくて、同時に動画をちょっと止めたりしながら、アウトプットの作業を同時にすることで、やっぱり理解は深まりますし、何を選んで書こうかなっていうところで、仕事で関わってるお子さんの顔思い浮かべたりしながら色を変えてマーカーを引いてみたり、すぐに現場で使えるようなテキストになると思うので、手元にはあった方がいいと思いました。
実際に受講してみていかがでしたか?
変わった部分というか自信に繋がったなって思う部分は結構あって、さっきも少しお話させてもらったんですけど、自分の経験とか出てきた知識とか、そこを繋ぐ内容であったり、その方向性が間違っていないというのが確認できたなってところで自信に繋がりましたし、そういう視点を得られたというのが変わった部分かなと思います。
受講前と比べてお子さんの変化はありましたか?
言葉を使う必要性を感じられるかどうかで発語の促しが決まる、というところで、例えばすごく気に入ってるウサギのぬいぐるみなんかを透明の中身が見えるビニール袋に入れて、上の方のフックに吊ったりして「あんなところにうさぎさんがいるよ」っていう声をかけると、「あった!」「取って」「だっこ」と言ったりするんです。本当に欲しいっていう気持ちから「何か言わなきゃ」っていう気持ちになってくれて、発語に繋がったなっていうのが一番大きいエピソードかなと思います。
今後もそうやって言葉を使うことによって望みが叶ったり、要求が通ったり欲しいものが手に入ったり、まずそういう一番お子さんが持ちやすい「自分が欲しい」っていう要求なんかを発語に繋げていけるといいなという風に思います。
この講座をどんな方にお勧めしたいですか?
発達支援の経験がすごく豊富な方で、すでに実践されていることが多いような方でも、その経験っていうのが1つの支援のきちんとした方法だっていうことを確認することができたり、また別の経験ともう1つの経験が繋がったりという発見などにも繋がると思うので、いわゆるベテランの先生なんかにも勧めたいと思います。あと、発達支援に関して未経験の方や経験の浅い方でも、最初に勉強した知識などから多様な視点でアプローチしていくことに繋がるというか、引き出しを増やすことができると思うのでそういう方にもいいのかなと思います。
私はどちらでもないかなという感じなんですけど、4,5年発達支援に携わっているのですが、浅い経験でも知識と経験を繋ぐことにも繋がっているかなという風に実感できたので皆さんにお勧めかなと思います。
発達障害児支援士資格認定講座とは
「発達障害児支援士資格認定講座」は、保育園・幼稚園・小学校・放課後等デイサービス・児童発達支援事業の職員の方など、発達が気になるお子さんと関わるすべての方を対象に、専門的な知識とスキルを向上させるためのプログラムとして開発されました。
- 友達にすぐ手を出してしまう子にどう対応するか
- パニックで叫ぶ子に、パニックを起こさないために、
事前にできる声かけとは何か? - どうしたら相手の気持ちがわかるようになるのか?
- 手先が不器用な子にどう対応するか?

子どもたちと関わる現場では、このようにたくさんの困りごとに対応する必要があります。そして、指導者はこうした困りごとに対して「一人ひとりに合ったアプローチをする」ことが求められています。
立ち歩く子への対処法。いくつ思いつきますか?
 たとえば、「授業中に座っていられなくて立ち歩く子」に、あなたならどのように対応するでしょうか?「立ち歩く理由」はいくつ思いつくでしょうか?その理由ごとの対処法はいくつ思いつきますか?対処法は、一つではないのです。
たとえば、「授業中に座っていられなくて立ち歩く子」に、あなたならどのように対応するでしょうか?「立ち歩く理由」はいくつ思いつくでしょうか?その理由ごとの対処法はいくつ思いつきますか?対処法は、一つではないのです。
もしあなたが「立ち歩かないでね」と注意することしかできないとしたら、そのアプローチはむしろ逆効果となって「望ましくない行動」を強化してしまう可能性があります。すると、全体の活動の進行をさらに難しくしてしまうのです。では、どうしたらよいのでしょうか。
気になる子どもへの対応は、事前準備が9割
 発達支援の専門家だけがもっている知識や経験に基づけば、「立ち歩いてから注意しても遅い」ということがわかります。そして、「立ち歩く理由は○○」だから「立ち歩かないようにするために、事前に○○をしておけばよい」と考えることができます。では、具体的にどのような準備をすればいいのか。あなたは知りたいと思いませんか?これがこの講座で学べることです。
発達支援の専門家だけがもっている知識や経験に基づけば、「立ち歩いてから注意しても遅い」ということがわかります。そして、「立ち歩く理由は○○」だから「立ち歩かないようにするために、事前に○○をしておけばよい」と考えることができます。では、具体的にどのような準備をすればいいのか。あなたは知りたいと思いませんか?これがこの講座で学べることです。
講座の特長
この講座で学べること
 この講座の最大の特長は、「その場しのぎの方法」や「場当たり的な指導」ではなく、「その子の未来につながる指導について学べる」という点です。
この講座の最大の特長は、「その場しのぎの方法」や「場当たり的な指導」ではなく、「その子の未来につながる指導について学べる」という点です。
 これは、操作性が未熟な子どもでも簡単にはさみの操作ができるようにサポートしてくれるバネつきのはさみです。はさみを使うのが苦手な子どもが、こうした支援グッズを活用することにより「できること」が広がるのはとても有意義なことです。ただ、そうした道具を与えるだけでは、「未来につながる指導」とは言えません。私たちが大切にしている価値観は、「その子自身の生きる力を伸ばす」ということです。では、「はさみをうまく使えない子」には具体的にどんな支援ができるでしょうか?
これは、操作性が未熟な子どもでも簡単にはさみの操作ができるようにサポートしてくれるバネつきのはさみです。はさみを使うのが苦手な子どもが、こうした支援グッズを活用することにより「できること」が広がるのはとても有意義なことです。ただ、そうした道具を与えるだけでは、「未来につながる指導」とは言えません。私たちが大切にしている価値観は、「その子自身の生きる力を伸ばす」ということです。では、「はさみをうまく使えない子」には具体的にどんな支援ができるでしょうか?
まず、はさみは手先で使うもので、身体全体から見ると「末端で行う運動」です。子どもの運動発達は、全身や腕全体、脚全体を使って行う運動(粗大運動と言います)から、ひじから下、手首から先、そして指先だけ、というようなより細かな運動(微細運動と言います)の順に発達していくと言われています。ですから、私たちははさみを使えない子に対して、単純に「はさみの練習をたくさんしよう」というアプローチはしません。
 その子が粗大運動も苦手とする場合は、まず身体全体の運動発達を促す必要があります。例えば、体育や運動遊びへの参加が消極的であれば、子どもが前向きに参加できるような工夫をして、運動習慣をつくるといったアプローチをしていきます。こうした取り組みは、「はさみの使い方」とは直接関係ないように思えるかもしれませんが「その子自身の力を伸ばす」という観点に立てば、「粗大運動から微細運動へと取り組み、スモールステップで発達を促していく」という長期的な関わりが必要であることが見えてくるのではないでしょうか。
その子が粗大運動も苦手とする場合は、まず身体全体の運動発達を促す必要があります。例えば、体育や運動遊びへの参加が消極的であれば、子どもが前向きに参加できるような工夫をして、運動習慣をつくるといったアプローチをしていきます。こうした取り組みは、「はさみの使い方」とは直接関係ないように思えるかもしれませんが「その子自身の力を伸ばす」という観点に立てば、「粗大運動から微細運動へと取り組み、スモールステップで発達を促していく」という長期的な関わりが必要であることが見えてくるのではないでしょうか。
ここでご紹介したのは、あくまで一例です。
この講座ではカリキュラム全体を通して、指導者自身が子どもの全体像をさまざまな角度から捉え、支援の引き出しを増やし、より適切な関わり方ができるようになることを目指しています。こうした「子どもの力そのものを伸ばす」指導が、集団の中で子どもたち一人ひとりの可能性を伸ばしていくことにつながるのです。
開発への想い
私たち四谷学院通信講座は、「だれでも才能を持っている」を理念に、一人でも多くの方々に「やればできる」「学ぶことは楽しい」という体験を通して、自己実現の喜びを味わっていただくための講座を開発してきました。
 「発達障害児支援士資格認定講座」も例外ではありません。
「発達障害児支援士資格認定講座」も例外ではありません。
本講座は、発達が気になる子どもたちやその周りにいる子どもや指導者の方、そしてご家族が、自己肯定感や自尊感情を育みながら、毎日を活き活きと過ごすことに寄与したいという思いで開発を進めてまいりました。
本講座で学ぶことで、志のある指導者・支援者の皆様が現場で役立つ支援力を身につけること、それが私たち講座開発の願いです。
学習システム
ポイントがぐんぐん頭に入ってくる講義動画
講義動画は、専門知識をスムーズに身につけられるよう、わかりやすさにこだわって作成しました。イメージしやすい実写映像も取り入れているので、学んだ傍から指導の現場に取り入れていただきやすい内容になっています。
初めて学習する内容もスモールステップでスムーズに理解&定着!
 実際の指導の現場で必要とされる専門的な知識を網羅し、適切な対応ができるようになるために必要な内容をスモールステップで学べるカリキュラムになっています。そのため、一つひとつステップをクリアしていくことで、着実に役立つ知識を吸収することができます。
実際の指導の現場で必要とされる専門的な知識を網羅し、適切な対応ができるようになるために必要な内容をスモールステップで学べるカリキュラムになっています。そのため、一つひとつステップをクリアしていくことで、着実に役立つ知識を吸収することができます。
週末45分×5ヵ月で支援のノウハウを習得
講義動画は1本あたり約15分。週に3本(約45分)程度のペースで視聴すると、およそ5ヵ月で全ステップの内容をすべて学ぶことができます。1年間の受講期間中であれば、いつでも・何度でも繰り返し視聴できるため、効率よく学習を進めることが可能です。
合格した先輩の声
講義動画のここがよかった
- 具体例で細かく、わかりやすい動画の講義のため、内容が理解しやすかった!
- 丁寧な解説や動画による耳と目からの学習なので学んだ内容が身につきやすかった!
- 一つの動画の時間が約10分なので、仕事しながら資格取得をするのに適していた!
- 具体的な例を動画で見れたので支援のイメージがしやすかった!
視聴チェックリスト
 講義動画の視聴スケジュールを管理できるリストをご用意しています。
講義動画の視聴スケジュールを管理できるリストをご用意しています。
こちらのチェックリストを活用しながら講義動画の視聴を進めることで、学習の進捗状況が一目で確認できます。
学習シート
 講義動画1本につき1枚、講義動画の概要をまとめた学習シートをご用意しています。
講義動画1本につき1枚、講義動画の概要をまとめた学習シートをご用意しています。
穴埋め式の学習シートに要点を書き込みながら講義動画を視聴いただくことで、効果的に学習の定着を図ることができます。ダウンロードしたデータに直接書き込む、印刷したものを手元に置いて手書きするなど、学習スタイルに応じてご活用いただけます。
受講期間終了後は、こちらの学習シートがオリジナルのテキストになるため、効率よく知識を総復習する上でもとても便利な学習ツールです。
合格した先輩の声
学習シートのここがよかった
- 動画で学んだ内容をまとめる際に学習シートがとても役立った!
- 学習シートがあることで復習する習慣が身についた
- シートが穴埋め式なので、自分で考えながら学ぶことができた

サンプル動画を無料で視聴できます。視聴用のURLをお送りいたしますので、下記のフォームよりお申込みください。
<発達障害児支援士資格認定講座「サンプル動画」をお送りします>というタイトルのメールが届かない場合は、こちらをご確認ください。
- 動画視聴をされた方には、講座の最新情報やキャンペーンの告知などもお送りします。
カリキュラム
現場で特別な支援を必要とする子どもに適切な支援をするための理論と実践について網羅しています。
あらゆる場面で、「目の前にいる子をどう伸ばすのか」という点から、長年の現場指導の経験から編み出された方法や考え方をわかりやすく学べるカリキュラムとなっています。
| 発達障害児支援士資格認定講座 学習内容 | |
|---|---|
| 指導の心得 |
|
| 特性への対応 |
|
| 問題行動への対応 |
|
| 身辺自立 |
|
| ソーシャルスキル |
|
受講の流れ
-

講義動画を自宅(スマホ・PC)で視聴する
(週末45分×5ヵ月)
※受講ぺースはご自身で調整できます -

発達障害児支援士 認定試験(自宅受験)
レポート課題・ケーススタディ課題の提出
※受講生専用ページにて -

発達障害児支援士資格 取得
 「発達障害児支援士」資格認定の証として、認定証と認定バッジを郵送いたします。
「発達障害児支援士」資格認定の証として、認定証と認定バッジを郵送いたします。
「発達障害児支援士®」は、日本発達障害支援協議会の認定資格です。
日本発達障害支援協議会ホームページ
講座概要
| 講座名 | 発達障害児支援士資格認定講座 |
|---|---|
| 資格名 | 発達障害児支援士® |
| 受講資格 | 特にありませんが、保育園・幼稚園・小学校の先生、児童発達支援事業・放課後デイサービスなどの福祉従事者、保護者、学生の方など、ベテランの方から未経験の方まで、幅広い層の皆さんにご受講いただいています。 |
| 受講形態 | 講義動画視聴 ※スクーリングはございません |
| 受講料 |
99,800円 (税込 109,780円) ※受験料を含む |
| 標準学習期間 | 6ヵ月 |
| 受講期間 | 1年 |
★当講座はオンライン完結講座です。
オンラインで必要な動画等の教材を確認し、認定試験の受験もできます。
(申し込み後、宅配便での教材お受け取り等のお手間をいただかずに学習をスタートできます。)
受講に必要な情報を記載した「受講開始のご案内メール」を翌営業日にお送りしますので、受信確認をお願いします。
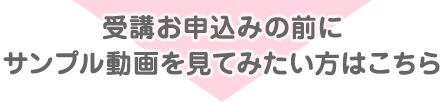

サンプル動画を無料で視聴できます。視聴用のURLをお送りいたしますので、下記のフォームよりお申込みください。
<発達障害児支援士資格認定講座「サンプル動画」をお送りします>というタイトルのメールが届かない場合は、こちらをご確認ください。
- 動画視聴をされた方には、講座の最新情報やキャンペーンの告知などもお送りします。
受講体験記
発達障害児支援士資格認定講座は、発達が気になるお子さまへの支援方法を学びたいという方ならどなたにでもご受講いただける講座です。発達支援に関する理論や実践について学び、適切な支援を行った結果、ご自身やお子さまがどのように変わったのか、以下をクリックして一人ひとりのストーリーをぜひご覧ください。
 さんのご紹介
さんのご紹介
| 発達支援のご経験 |
小学校(特別支援学級担任) 児童発達支援事業部、放課後等デイサービスなど |
|---|---|
| 経験年数 | 15-20年 |
続きを読む
「発達障害児支援士」を目指した理由は?
特別支援学校の教員免許は持っているんですけど、さらに専門性を高めて、公でも名乗れるような資格がさらにあればなと思って、受講したいなと思いました。
子どもも障害がある子なので、日々、どういう風に対応するのか考えているので、そういった意味でも勉強になるかなと思いました。
これまで困っていたことは?
児童発達支援施設で今は働いてるんですけど、親御さんへの対応とか、お子さんでもやっぱり色々いて。
小さいお子さんなので、まだまだお母さん達の方もどういう風に子育てしていけばいいかなと悩まれている方も多いので、そういった方により正しいことを上手にお伝えしたいなっていうのは、日々感じてました。
保護者から多い相談は?
排泄自立とか、そういう身の回りのことをどういう風に身につけたらいいのかとか、かんしゃくとかそういうお子さんもいるので困ってるっていうようなことはよく聞きますね。
指導の「引き出しを増やす」ことは大切ですか?
(保護者の悩みに対して)その都度思ったことは返すんですけど、やっぱり分からないことは「ちょっと相談しますね」っていう形で軽く答えてしまわないようにしてますね。
そういう会議は日々もつ機会があるのでその中で他の担当の方とも相談して返事をするようにはしてます。
なのでも他のスタッフも同じように(引き出しを増やしたいと)思ってるんじゃないかなと思います。
資格取得後、どんな変化がありましたか?
大きな資格がひとつ取れたっていうことで、自分の中でそれだけ知識専門性を高められたなっていう自信に繋がったなぁと思っています。
(発達障害児支援士資格認定講座で)受講した内容っていうのはすごい基盤だと思うんですけど、自分が指導する時にどうしようかなって思った時に「あそこでは何て言ってたかな?」みたいな振り返る“辞書”というか。
あそこでなんて言ってたかって思う“考える土台”になった、そういうところは変わりました。
学習内容の難易度は?
難易度っていうのは、基礎的なことだなっていうのは感じました。
ただやっぱり、ずっと指導していくと自分の癖みたいなのが出てくるんですけど、こういうのをもう一度学び直すと「ちょっとこういうとこ良くなかったな」っていう反省の機会にはなるなって風には感じます。
具体的にどんな反省をされましたか?
講座の中でよく出てきたのは「1つの課題につき1つの目標を立てる」っていうのがよく言葉で出てきてたんですけど、やっぱりそれを聞くたびに、自分はもっと求めてしまって1つの課題につき1つの目標っていうのができてないなっていうことを感じることがよくありましたね。
(お子さまが施設に通うのが)週1回とかだと毎日じゃないので「今来てるうちに」とか思ってしまうと、ついついやりすぎてしまうっていうようなところがあるかなっていう風なのは。日々反省ですね。
パソコン、スマートフォンどちらで勉強しましたか?
両方、使いはしたんですけど、主にはパソコンです。
画面が大きい方が見やすいっていうのと、メモを取るとか座った状態で机があるところでパソコンを開いてっていう方がやりやすかったなと自分は思います。
ただ空いた時間にスマホでパパッと見れるのも、本当に忙しい方とか、それもいいなとは思うんですけど。
普段、どんな風に勉強を進めましたか?
私は受講する時は、例えば子どもがいる時じゃなくって、仕事がある日とかじゃなくって、もうそれに集中できる日っていうのを、メモを取りながら聞き落とすことがないように受けたいなって、すごいちょっと力みすぎるって言うか、そういうような勢いだったので、もう、やる日はやるっていうので。
忙しい中でそういう時間を作るので、結構割と見る時はたくさん見るっていう感じで。
(学習)期間も、働きながら子育てしながらだったので、丸々1年、期限いっぱい使って行いました。
学習シートがあったので(学習シートの書き込み用)カッコに「これ何だ?」って思って埋められなかった時は、もう1回最初から(講義動画を)見ましたね。
学習シートはどんな風に活用しましたか?
一番最初に全部プリントアウトして(学習シートを)テキストにするつもりでずっとそこにメモしていってました。
まだ20代とかの方はわからないですけど、紙に書いて勉強してきたようなところがあるので、やっぱり紙のほうがやった感はありますね。
特に印象に残ったテーマは?
どこの内容も納得しながら、全て自分が知ってるわけじゃもちろんないので。どこのテーマも「あ、そうなんだ」っていう風に結構まんべんなく、それはちょっと感じたかなと思います。
基本的なことでも、うがいの仕方とかでも、どれが易しい方法で、どれがちょっと1ランクアップなのかとかいうのもそこで「あ、そうなんだ」「あ!そっか、そうだったなぁ」そういうような感じでしたので、全てにやっぱりそういう部分があったかなっていう風に思います。
もっと勉強したいテーマはありましたか?
ここで学んだことは基礎のことだと思うので、やっぱりその現場に出るとそれをどう使ってどうやって行くかっていうところになってくると思うんで。
ケーススタディを考える場っていうのがあったら、応用編みたいな感じでそういうのがあったらいいかなって。もっと考えていきたいなっていう風に思いました。
認定試験を受験したご感想は?
一通り全部終わってから認定試験は行いました。
ケーススタディとかだったら10個とか書くことがあって「あら、7個しか思いついてないなー」っていう時とかは、書いてたメモとか見直したり動画をもう一度見たりして取り組みました。
こういうことあるなって、とても良い勉強だったなっていうのは思います。
基本で学んだことっていうのは学んだことで、実際の現場ってこういうケーススタディの集まりだと思うんですね。
「こういう子いたらどうするかなー?」みたいなことを考えながら取り組みました。
よくあるご質問
教材や受講方法について
手続き完了までの大まかな流れは以下の通りです。
受講お申込み
決意表明を入力
カートに入れる
申込む
注文手続きへ
申込者情報やクレジットカード情報を入力して、手続き完了です。
※お申込みはWEB申込のみ、支払いはクレジットカードのみとなります。
お申込み後、受講に必要な情報を記載したメールを翌営業日にお送りします。
学びたいという気持ちがあればどなたでも受講できます。
講義動画では具体的な事例を取り上げ、専門用語もできるだけかみ砕いて説明をしていますので、発達支援の現場で指導されている方はもちろん、発達支援について初めて学ぶ方でも受講いただけます。
受講中の皆さんの声はこちら
幼稚園・保育園・小学校、児童発達支援事業所や放課後等デイサービスで発達支援に携わっている方はもちろん、作業療法士などのリハビリテーション専門職の方、幼児教室の講師、インストラクターの他、発達支援の現場に就職・転職を検討されている方も「発達障害児支援士」の資格取得を目指して受講されています。
質問制度はご用意しておりません。発達支援について初めて勉強される方でもスムーズに学習を進められるよう具体的な事例を取り上げ、専門用語もできるだけかみ砕いて説明をしていますのでご安心ください。もし、学習を進める中で質問したいことが出てきた場合は、月額制の発達支援プレミアム会員にご入会いただくと、学習内容に関するご質問だけでなく、現場で抱えている困り事についてのご相談などもお送りいただけます(講座の特性上、資格試験に関するご質問は受付できませんのでご了承ください)。ご入会後30日間は無料で利用いただけますので、ぜひご活用ください。
当講座はオンライン動画で学ぶ形式となっており、テキスト等の教材の発送はございません。
お申込の際に入力いただいたメールアドレスへ、動画視聴サイト「受講生専用ページ」に新規登録するためのIDとパスワードを翌営業日に送信いたします。
講義動画は「受講生専用ページ」にログインをして視聴していただきます。
受講期間中は、すべての動画を、いつでも何度でもご視聴いただけます。忙しい毎日の中でも、あなたのペースに合わせて学習を進めてください。
当講座のオンライン動画は、パソコンやスマートフォンで視聴が可能です。また、認定試験については、インターネットの受講生専用ページの所定フォームに、直接入力いただく形式になっております。スマートフォンで受験される場合、画面の大きさや文字入力の際にご不便を感じる可能性がございますので、認定試験についてはパソコンでの受験をお勧めしております。スマートフォンでも受験自体は可能です。
発達障害児支援士講座については、原則クレジットカードでのお支払いをお願いしております。
銀行振込(一括払いのみ)でのお支払いをご希望の場合はこちらからご連絡ください。
認定試験について
事例(ケーススタディ)について、ご自身で考えて答える課題です。
指定された事例について、これまでの学習を元にどのような指導が可能であるかを具体的に考えて答えていただくレポート形式の課題です。答えは一つではありませんし、制限時間もありませんから、じっくりと取り組んでいただけます。
すでに現場で活躍されている方は、さらに引き出しが増えたことを実感できるでしょう。まだ子どもと接する機会がない方は、ケーススタディ課題に取り組むこと自体が、良い学びになるでしょう。
受講期間内に1回、全ての講義動画を終えた後、お好きなタイミングで受験していただけます。
レポート課題・ケーススタディ課題の両方において、発達障害児支援士としての資質が十分に備わっていると判断された場合に「可」と評価され、合格となります。発達障害児支援士としての考え方や知識の習得が不十分と見なされた場合には、「不可」と評価され、不合格となります。
はい、受講期間中であれば1回につき10,000円(税込)で再受験ができます。
評価が「不可」であった場合、再受験申込のご案内をメールをお送りします。
そちらの案内にしたがってお手続きいただいた後、再度認定試験をご提出ください。
当講座が認定試験の提出を受け付けてから原則2週間以内に、メールで通知します。合格の場合は認定証と認定バッジを送付します。
郵送にてお送りします。認定証を持った笑顔のお写真やバッジを身につけた喜びのお写真を、体験記とともにぜひ当講座へお寄せください。
資格について
記載いただけます。当資格は日本発達障害支援協議会が認定する資格です。
保育園や幼稚園、託児所等はもちろんのこと、発達障害児のための支援施設だけでなく、一般的な子どものサポートを行う施設やスクール、塾などでも、スキルや資格を活かしてご活躍いただけます。
有効期限は設けていません。更新手続きも不要です。
発達障害プレミアム会員制度がございます。
講座在籍中、もしくは修了後にお申し込みが可能です。詳しくは、お申し込み後、受講生専用ページ等でご確認ください。
修得した知識や考え方、資格を活かして発達障害児支援士として様々な活動が可能です。発達支援事業の開設については、様々な条件がございますので、最寄りの役所にお問い合わせください。
発達障害児者への支援を充実させるべく、教育・福祉・就労先で当事者の支援にあたる方やご家族を対象に、人材育成・資格認定を行っています。「発達障害児支援士資格認定講座」は、日本発達障害支援協議会の認定研修として、四谷学院に運営を委託しています。
そのほか
当講座はほとんどの方がお仕事と両立しながら受講されています。1本あたりの動画は約15分。週に3本(約45分)のペースで視聴すると、およそ5ヵ月で全ステップの内容を学べます。1本ずつの講義動画はコンパクトでありながら内容は濃く、受講期間は1年と余裕があるため、お忙しい方でも安心してご受講いただけます。
オンライン講座のため、パンフレットのご用意はございません。
そのかわりに、実際の動画を確認いただける「サンプル動画」を公開しています。
以下の原因が考えられます。まずはご確認ください。
(1)入力されたメールアドレスが間違っている。
→フォームに正しいメールアドレスをご入力し、送信してください。
(2)メールソフトやプロバイダ側の設定などで、迷惑メールと判断されている。
→迷惑メールフォルダ等をご確認ください。迷惑メールフォルダにも見当たらない場合には、「yotsuyagakuin.com」「info.yotsuyagakuin.com」のドメイン指定受信を設定してください。
その後、事務局までご連絡ください。
迷惑メールの設定に関しては、ご契約しているインターネットプロバイダーにお問合せください。
並行しての受講が可能です。
特に保育士試験の受験科目が残り数科目という方は、これまでの学習の知識を活かしつつ、さらに発達障害に特化して学ぶことで、保育士としての「強み」を伸ばすことが期待されます。
55レッスンは、家庭療育をサポートすることが目的となっています。
発達障害のあるお子さまが取り組みやすく、保護者様が指導しやすい教材をご提供します。さらに、通信講座にもかかわらず手厚い指導サポートがついていることが大きな特徴です。
55レッスンはこちら
一方で、発達障害児支援士資格認定講座は、主に保育園・幼稚園・小学校・児童支援施設など、集団における発達支援について学び、資格を取得することが目的となっています。
法人・団体向けの「研修コース」がございます。詳しくは「発達障害児支援 研修コース」のホームページをご覧ください。
こちらのページでご案内しています。
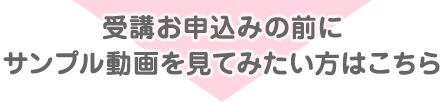

サンプル動画を無料で視聴できます。視聴用のURLをお送りいたしますので、下記のフォームよりお申込みください。
<発達障害児支援士資格認定講座「サンプル動画」をお送りします>というタイトルのメールが届かない場合は、こちらをご確認ください。
- 動画視聴をされた方には、講座の最新情報やキャンペーンの告知などもお送りします。