
こんにちは、55レッスンの生田です。
先日、55レッスン取材班で「よこはま発達クリニック」を訪れました。
本記事では、医療機関の受診の参考にしていただけるようよこはま発達クリニック副院長の宇野洋太先生へのインタビューを2回にわたってお伝えします。
診断を下せるのは医師
「もしかしたら、うちの子って発達障害なのかな?」
この問いの次に浮かぶのが、「誰に聞けばいいんだろう?どこに行けば教えてくれるんだろう?」という疑問ではないでしょうか。
発達障害の診断を下せるのは、医師です。
とはいえ、どこの病院でもよいというわけではありません。まずはそんな疑問を聞いていただきました。

よこはま発達クリニック 副院長 宇野洋太先生
このよこはま発達クリニックも「児童精神科」です。
児童精神科の医師のバックグラウンドは、大きく2つに分けることができます。
1つは、精神科から始まり、子どもの精神に特化していくというケースで、うちの3名の医師のうち2名がこのケースに該当します。
もう1つは、元々小児科医として働いて、そこから子どもの精神を診るようになったというケースで、うちの残りの1名もこちらに該当します。全体で見ると、半々くらいでしょうか。
当院は専門機関ではありませんが、他に被虐待経験のある方を専門に診ている児童精神科医も多くおります。
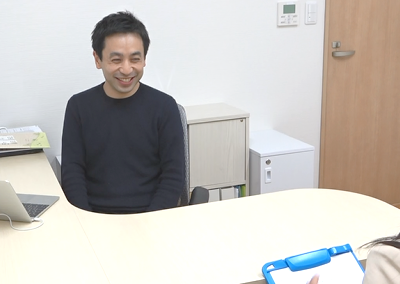
次に、発達歴について確認します。赤ちゃんの頃や子どもの頃の様子を具体的に聞いていきます。どんな遊びが好きだったか、といったことまで教えてもらいます。こういった話を詳しく丁寧に聞き取るのが、初診の主な内容ですね。
後日、今度は心理士が発達検査をとります。発達検査をとることで、お子さんの得意・不得意であったり、発達が年齢相応かといったことが把握できます。
また、認知特性をつかむことも検査の目的の1つです。検査結果上は同じIQだったとしても、認知プロセスは人によって様々です。同じ答えを出していても、答えの出し方は人それぞれだったりしますよね。たとえば、ストーリーを読み取る時、登場人物を手掛かりに流れを読み取る方もいれば、背景に着目して状況を読み取る方もおられます。
発達経過や現在の状況、検査結果や行動観察での様子、といった情報が揃うと、診断、という流れになります。診断内容を踏まえて、今後どのようにしていくといいのか、一緒に方略を立てていきます。
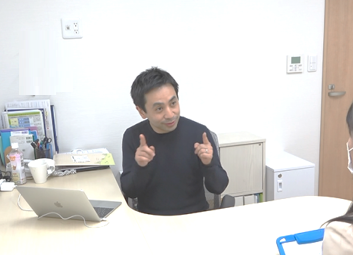
知的障害で療育手帳をとる、というケースなら幼児期など早いうちにとる方が多いです。
精神障害者保健福祉手帳の方は、障害者雇用枠での就労を見据えた時にとる方が多いです。高校生くらいの年代であったり、成人して一般就労していた方が障害者雇用に切り替える際にとるケースが多いように思います。
カウンセリングルームで行われるカウンセリングや検査は、保険適用外となります。
宇野先生は大変穏やかなやさしい印象の先生でした。お話もとても丁寧に、そして詳しく聞かせていただきました。
「こんな感じなんだ!」と児童精神科の具体的なイメージが広がってきたのではないでしょうか?
予約してから初診まで、待つ期間があることを考えると、「気になるな」と思ったらまずは早めに連絡を取ってみると良さそうですね。
「インタビューその2」に続きます!

このブログは、四谷学院「発達支援チーム」が書いています。
10年以上にわたり、発達障害のある子どもたちとご家庭を支援。さらに、支援者・理解者を増やしていくべく、発達障害児支援士・ライフスキルトレーナー資格など、人材育成にも尽力しています。
支援してきたご家庭は6,500以上。 発達障害児支援士は2,000人を超えました。ご家庭から支援施設まで、また初学者からベテランまで幅広く、支援に関わる方々のための教材作成や指導ノウハウをお伝えしています。
このブログでは、発達障害のあるお子様をはじめ保護者の方やご家族、支援者の方が笑顔で毎日を過ごせるよう、療育・発達支援のヒントを発信していきます。





コメント