
こんにちは、四谷学院の生田です。
発達障害のあるお子さんの保護者から、
「子どもがパニックになってしまったとき、どのように対応すればいい?」
というご質問をいただくことがあります。
今回の記事では、実際に寄せられたご質問をもとに「パニックへの働きかけ方」について、55レッスンの教材編集に携わっている武蔵野東学園の先生からアドバイスをいただきましたので、みなさんにも共有いたします。

目次
電車やバスでパニック!

※写真はイメージです
ご質問の内容を紹介します。
(なお、ご質問の内容は実際のものをアレンジしています。)
子どもと水族館へ遊びに出かけたときの話です。
水族館まではバスを利用しましたが、混んでいて座ることができませんでした。
それほど長い時間ではなかったのですが、それまで子どもにとって「バス=座って乗るもの」だったので、立ったまま、という状況に納得がいかなかったようです。
座れないことでパニックになった子どもは、車内で「座りたかった」と何度も何度も言い続けました。
水族館に到着してからも状況は変わらず、気持ちの切替に非常に時間がかかりました。
前から子どもも楽しみにしていた水族館だったのですが、こうしたことがあると、親も気分が落ち込んでしまいます。
以前にも同じようなことがありました。本人には
「空いていたら座れるけれど、混んでいる時や他に座る人がいる時は座れない」
と説明はしています。
頭では分かっているようでしたが、
「でも、自分も疲れているから座りたい」
と言います。
このように、自分の思い通りにいかないからといってパニックになってしまう場合、親はどうすればよかったのでしょうか?
パニックへの働きかけ

支援の基本的な考えとして、以下の3つのステップがあります。
1.事態を予想する
お子さまの行動の傾向を知り、イベントなどの環境の変化に際してあらかじめ危惧されることを予想します。
今回は、思い通りにいかないとパニックを起こしてしまうお子さまの傾向から
「バスが混んでいたら座りたいと言い続けるかもしれない」
「館内を回る順番にこだわるかもしれない」
「見たかったショーが見られなかったら、気持ちが崩れるかもしれない」
などの予想が立てられます。
2.事前準備をする
次は、予想される事態に対して、事前準備をします。
発達障害のあるお子さんは先の見通しが立たないことが苦手な場合が多いです。
そのため、事前に説明をすることはとても大切です。
「明日はバスに乗るよ。もしかして混んでいて、座れないかも。そしたら立って乗ろうね」
と、あらかじめお子さまに説明をしておきます。
このとき、当日や前日に告知するのではなく、なるべく余裕をもって繰り返し伝えておけると、お子さまも納得しやすくなります。
また、気持ちを落ち着けられる雰囲気をつくることも重要です。
たとえば、好きな本、動画、ゲームなど、お子さまの安心・気分転換に役立つグッズを用意しておくことが有効な場合があります。
気持ちを安定させられるグッズがあることは、実際に使用するかどうかにかかわらず、お子さまにとって安心につながることがあるからです。
3.事態が悪化した場合の対処法を考えておく
それでも事態が悪化することがあるかもしれませんね。
なるべく事前準備をした上で、困った行動が起きた場合は、基本的には反応しないことが鉄則です。
もちろん、場合によっては、子どものパニックを助長しないように途中下車する、好きなおかしを与える、などの対応が必要になることもあるでしょう。
ただし、このような対応を繰り返すと、かんしゃくを起こすとおかしが食べられるといった誤った学習をしてしまう可能性もあるので、注意が必要です。
ソーシャルストーリーの技法で事前学習をする

今回のように、あらかじめ決まっているイベントに向けての事前準備だけでなく、普段からハプニングに対処できるようになるためにご家庭でできる練習もあります。
ソーシャルストーリーの技法を活かす、という方法です。
これは、たとえばバスや車内の様子の写真、絵を使って、予測される困難に遭ったときにどうするべきかを、自分たちを主人公に見立て、ストーリー仕立てで説明する、というものです。
要所要所でどうすることが正解なのかを、お子さまと一緒に考えてみましょう。
この時、正解でも不正解でも、「自分で考えた」ことを評価して、ポジティブな声かけをすることが大切です。
さらに文章化してみる

さらには、ハプニングへの対応方法を大人と一緒に考えた後、文章化して理解を深める方法があります。
武蔵野東教育センターや55レッスンでは、「こんなときどうする?」「考えてみよう」と、お子さま自身で考えてもらう学習カリキュラムがあります。
プリント上に、ある場面を想定した挿絵とその場面の説明があり、その下に「こんなときどうするか」を書いていくというものです。
実際の場面に遭遇したときや、ストレスの中では落ち着いて考えられないことが多いので、こうした事前学習は効果的と言われています。
家の中での接し方を振り返る

家の中で同じような事が起きたとき、どのように対応しているでしょうか。
ほかに迷惑がかからないため、外とは違う対応になっていませんか?
状況によって対応が変わってしまうと、「家ではいいのになんで外ではだめなの?」という風に、子どもも混乱してしまいます。
家の中でのトラブルも、外出先でのトラブルと同じように、
「どうすることが正解なのか?」
をお子さまに理解してもらうことを試みましょう。
スモールステップで、少しずつ柔軟性を身につけていけるといいですね。
体験から学ぶことの必要性

事前準備によってお子さまのパニックを防ぐことは大切ですが、同時に、体験を通じて学ぶことも大切です。
今回のようなことは、お子さまそしてご家族にとってもむずかしい経験だったかもしれませんね。
でも、親子それぞれ、そこから学んだこともあったはずです。
失敗を恐れて外に出ない、という選択はなるべく避けて、ぜひ、いろいろな体験をさせてあげてほしいと思います。
体験を重ねる中で、お子さまは見通しが持ちやすくなりますし、保護者も事前準備がうまくいきやすくなることでしょう。
また、パニックになる経緯として、状況を理解する力や、それまでの経験が不十分なために不安になり、混乱する、というケースも多いようです。
お子さまに合った環境を整えていくことはもちろん大切ですが、成長することによって自然に覚えていくこと、できるようになることもありますから、長い目で見て見守るとう姿勢ももっておきたいものですね。
四谷学院の55レッスンでは、段階的にソーシャルスキルを磨くことができます。
課題を通じて学んだことや、コミュニケーションシートを通じた担任の先生からの具体的なアドバイスは、お子さまの日常生活にもよい影響をもたらします。
詳しくはホームページをご覧ください。無料で資料もお届けいたしますよ。

このブログは、四谷学院「発達支援チーム」が書いています。
10年以上にわたり、発達障害のある子どもたちとご家庭を支援。さらに、支援者・理解者を増やしていくべく、発達障害児支援士・ライフスキルトレーナー資格など、人材育成にも尽力しています。
支援してきたご家庭は6,500以上。 発達障害児支援士は2,000人を超えました。ご家庭から支援施設まで、また初学者からベテランまで幅広く、支援に関わる方々のための教材作成や指導ノウハウをお伝えしています。
このブログでは、発達障害のあるお子様をはじめ保護者の方やご家族、支援者の方が笑顔で毎日を過ごせるよう、療育・発達支援のヒントを発信していきます。




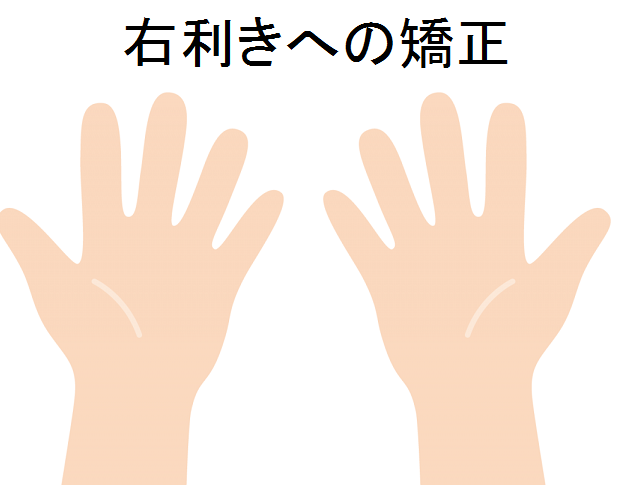
コメント