
こんにちは、四谷学院の生田です。
療育を進めていく中で、お子さまの変化に気づくという保護者の方は多いのではないでしょうか?
その背景には環境の変化があります。
それは、家族の変化ともいえるでしょう。
この記事では、家庭環境が与える子どもへの影響をお話しします。
子どもは大人の感情を敏感に察知する

お子さまは、大人の感情に波にとても敏感です。
「子どもが笑顔でいると親は嬉しい」という言葉はよく耳にすると思いますが、親が笑顔でいると子どももうれしいのです。
その逆も言えます。
親が不安や心配に押しつぶされそうになったり、イライラとして表に出てしまったり・・・すると子どもも心身が不安定になってしまい、今までできたはずのことさえできなくなってしまう、そうした話は珍しいものではありません。
発達の土台にあるもの

たとえば、「言葉が遅い」というお悩みがあったとしましょう。
その時何をすべきか…いろいろな指導・支援が考えられると思いますが、「心身の発達が土台にある」ということを忘れてはなりません。
生活のリズムを整えること
家族がニコニコ楽しく過ごしていること
こうしたことが、子どもの発達には大きく影響します。
もしもお母さんが毎日不安そうな顔をして、腫物を触るように子どもと接していたら・・・
もしもお父さんが毎日難しい顔をして、イライラと子どもに怒鳴っていたら・・・
どうでしょうか?
もしもお母さんが毎日ニコニコして、子どもに明るく声をかけていたら・・・
もしもお父さんが毎日穏やかな笑顔で、子どもをぎゅっとハグしていたら・・・
どちらの方が、子どもの発育・発達に良い影響を与えると思いますか?
もちろん、ニコニコ笑顔で過ごす方ですよね?
的確なアドバイスとモチベーションアップ

ここで1つ、保護者の気持ちを変えた出来事をご紹介します。
四谷学院の療育講座「55レッスン」をご受講中の方の生のお声です。
コミュニケーションシートに書いた一つひとつの事柄すべてについてコメントやアドバイスを丁寧にいただき、本当にありがとうございます。
課題について「こういうやり方だと上手くいくのでは?」「このような発展課題もある」と具体的な方法を教えていただき、その他の生活面の事柄もアドバイスいただき、どれも大変参考になるものばかりでした。
こちらが知りたいと思っていることを(コミュニケーションシートの拙い文章から読み取っていただき)的確にアドバイスいただけてとても感激しました!
まだ1回目ながら、文面からはうちの子どもの特性を理解していただき、考えていただいていると感じましたし、子どもも私(母)も褒めていただきモチベーションが上がりました!
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
いかがでしょうか?
きっと多くの療育では「的確なアドバイス」を受けることができると思います。
専門家ならではの視点のコメントは、きっと普段のお子様とのやりとりの中でも生かされていくことでしょう。
しかしそれ以上に大切なのは、保護者の療育のモチベーションが上がることです。
なぜ保護者は毎日笑顔でいられないのか?

理由はいくつもあると思いますが、1つには「不安」が挙げられるでしょう。
そして不安の原因として
②見通しが持てない
こうしたことが考えられます。
でも・・・
逆に言えば
正しいやり方で進んでいるとわかり、見通しが持てれば、毎日笑顔でいられます。
最初にご紹介した、55レッスンを受講中のお子様のお母さまからの感想を見てみるとこんな言葉がありましたよね。
課題について「こういうやり方だと上手くいくのでは?」「このような発展課題もある」と具体的な方法を教えてもらえた
子どもも私(母)も褒めてもらった
進むべき方向が見えていて、今の子どもと自分をほめてもらえる。
これはとっても大切なことだと思います。
こうした言葉をいただくたびに、「55レッスン」はお子さんのためだけでなく、保護者のためでもある講座だなと感じています。
発達障害の原因は、家庭でのしつけではありません。
まだはっきりとわかっていませんが、脳の障害が原因と考えられています。
四谷学院の療育講座「55レッスン」にご興味を持っていただけましたら、ぜひホームページをご覧ください。
無料の判定テストもお渡ししています。

このブログは、四谷学院「発達支援チーム」が書いています。
10年以上にわたり、発達障害のある子どもたちとご家庭を支援。さらに、支援者・理解者を増やしていくべく、発達障害児支援士・ライフスキルトレーナー資格など、人材育成にも尽力しています。
支援してきたご家庭は6,500以上。 発達障害児支援士は2,000人を超えました。ご家庭から支援施設まで、また初学者からベテランまで幅広く、支援に関わる方々のための教材作成や指導ノウハウをお伝えしています。
このブログでは、発達障害のあるお子様をはじめ保護者の方やご家族、支援者の方が笑顔で毎日を過ごせるよう、療育・発達支援のヒントを発信していきます。




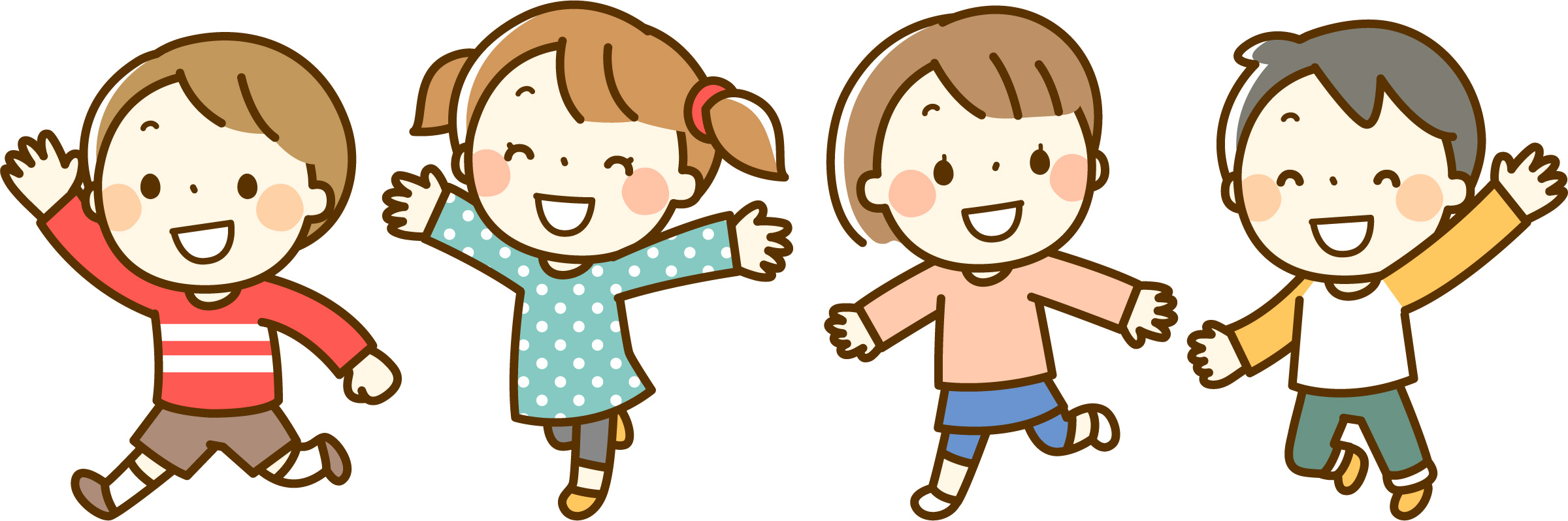
コメント