
こんにちは、四谷学院の生田です。
お子様に注意するとき、ついつい感情的になっていませんか?
「なんでできないの!」「ちがうでしょ!」
大きな声を出してしまって、子どももギャン泣き。
親もあとで反省・・・よくいただくご相談です。
この記事では、「効果的な叱り方・褒め方」について解説をご紹介します。
目次
叱る目的は何か?

お子様を叱るときには、叱る目的は何かを明らかにしましょう。
そのうえで、叱る必要があるかの判断を慎重にする必要があります。
大人にとっては当たり前のことでも、子どもにとっては
「え?なんで?」
ということもあります。
子どもが叱られた意味を理解できなければ、親の嫌悪や恐怖だけがお子様に伝わってしまうのです。
そうした状況が続くと、他害や自傷行為などの問題行動につながることがあるので注意する必要があります。
叱られることは強い刺激です

親をはじめ、大人に叱られることは、お子様にとってとても強い刺激であるということを理解しましょう。
お子様が叱られた意味を認知できない場合、かえってその行動を強化してしまう可能性があります。
つまり、注目や刺激が欲しくて、叱られるための行動を故意に繰り返してしまうこともあるのです。
感情的になる理由は?

お子様を叱るときに、感情的になってしまうのは、なぜでしょう?
もしかすると、何度注意してもお子様の態度や行動が変わらないからかもしれません。
お子様に同じ注意を繰り返しているのなら、現段階では期待や要求が高すぎると考えた方がよいでしょう。
「今はできなくても仕方ないのかも」と、捉え方を変えてみることも時には必要です。
スモールステップで褒める機会をつくる
大きな段差を上るのは、とても大変です。
体力も必要ですし、メゲナイ強い心も求められます。
では、その段差を小さくしてみたらどうでしょう?
スモールステップを意識して、段階的な目標を設けます。
すると、「できる」という達成感をお子様も、そして親も感じることができるんです。
スモールステップは、子どもを褒めるきっかけを作ることができます。
注意を引く言葉かけを
お子様の注意を引いて、対面で話すことも大切です。
聞いてほしいときに投げかける言葉、たとえば「聞いてください」などを決めておくとよいかもしれません。
同じ言葉かけを続けることで、「あ、聞く時間だ」と注目できるようになるでしょう。
叱るときは「具体的に」

お子様を注意する時や褒める時は、具体的に伝えましょう。
たとえば
「今日はおりこうだったね」より「電車の中で静かにしていられてよかったよ」などです。
時間が経過してからでは何のことかわからないこともあるので、お子様の行動の直後に伝えるというタイミングの工夫も重要です。
注意してもなかなか行動が直らない場合は、指示が長すぎることもあります。
本人が理解している言葉を繰り返しましょう。
正しい行動を教えることが効果的
お子様の態度や行動を叱りたくなることはあるでしょう。
しかし、叱るより「正しい行動をわかるように教えてあげること」の方が効果的です。
ダメと言われても、ではどうすればよいかをわかっていないと、正しい行動はとれません。
代表的な例をご紹介します。
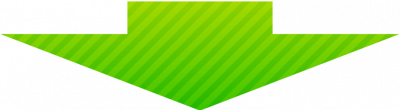
「廊下は歩きます」

正しい行動を促す注意が、ただ叱るよりも効果的なんです。正しい行動を明確に伝えてあげましょう。
ジェスチャーや絵カードも有効
言葉だけだと意識を向けにくい・理解しにくいお子様に対しては、ジェスチェーや絵カードが有効です。
視覚に訴える方法を試してみましょう。
効果的な子どもの叱り方・褒め方:まとめ

「叱る」「褒める」
どちらにしても、どのような方法ならメッセージがお子様に伝わりやすいかを常に考えるようにすると、冷静に対処しやすくなるでしょう。
四谷学院の療育プログラム(55レッスン)では、お子様の「自己肯定感」を大切にします。
達成感を得られるスモールステップで
「できた!」「わかった!」
を増やしていきます。
くわしくはホームページをご覧ください。無料で資料もお送りしています。

このブログは、四谷学院「発達支援チーム」が書いています。
10年以上にわたり、発達障害のある子どもたちとご家庭を支援。さらに、支援者・理解者を増やしていくべく、発達障害児支援士・ライフスキルトレーナー資格など、人材育成にも尽力しています。
支援してきたご家庭は6,500以上。 発達障害児支援士は2,000人を超えました。ご家庭から支援施設まで、また初学者からベテランまで幅広く、支援に関わる方々のための教材作成や指導ノウハウをお伝えしています。
このブログでは、発達障害のあるお子様をはじめ保護者の方やご家族、支援者の方が笑顔で毎日を過ごせるよう、療育・発達支援のヒントを発信していきます。




コメント