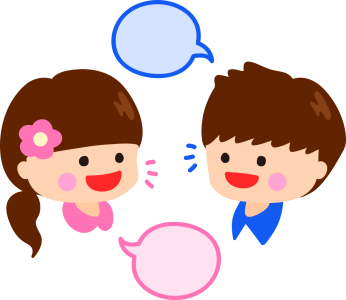
こんにちは、55レッスンの生田です。
この記事では、「とっさのときに言葉が出てこず、手が出てしまう・・・」
そんなお子様についての悩みと担任の先生からのアドバイスをご紹介いたします。
とっさに言葉が出ない
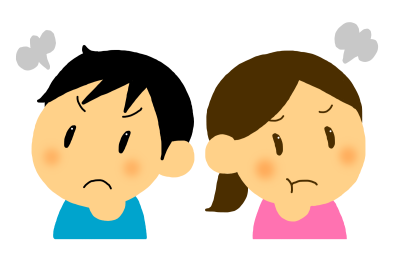
だから、何も言わずに奪い取ってしまう・・・
だから、そのお友達を叩いてしまう・・・
言葉より先に手が出るので、周りのお友達から「乱暴な子」と思われてしまうかもしれません。
このような社会的に不適切に見える行動を減らすにはどうしたらいいでしょうか?
ソーシャルスキル・対人関係スキルを高める

「入れて」や「やめて」などの言葉が瞬間的に出ない時には、その場で状況に合う言葉の表現を教えてあげたり、相手の気持ちを説明してあげたりすると理解しやすいでしょう。
可能であれば、手が出そうになった時に、その手をとめて
「“貸して”だよね」
というように、適切な関わりができるよう誘導してあげましょう。
「貸して?」と言ったら、貸してもらえたという成功体験を得られるようにします。
右脳と左脳の連携
言葉を組み立てるのは、左脳の働きです。また、相手の感情やその場の状況を察知するのは、右脳の働きです。
左脳と右脳がうまく連携すると、状況に合わせた言葉の活用が上手になると言われています。
そこで、左脳と右脳が連携する経験が重なるよう正中線を交差した動きを生活や遊びの中に取り入れることも良いでしょう。
正中線は眉間から股間までをつなぐ1本の線で、妊娠したときにおなかに表れることも多いのですが、実は妊婦さんだけでなく誰でもあるものです。受精卵のときの細胞分裂の名残と言われています。
こんな感じです。

たとえば・・・
(2)服の右肩につけた洗濯バサミを左手で取らせます。
このように、体の中心を越えながらとるという動き、つまり体の中心を反対側に越える経験を増やします。
ほかにも、右ひざを左手でタッチ、左ひざを右手でタッチ、を交互に繰り返す運動(クロスクロール)なども、簡単にできて、音楽に乗って楽しむこともできてオススメです。
四谷学院の55レッスンでは、一人ひとりに担任の先生がついて家庭療育をサポートいたします!課題を通して個別にアドバイスをいたしますので、安心です!

このブログは、四谷学院「発達支援チーム」が書いています。
10年以上にわたり、発達障害のある子どもたちとご家庭を支援。さらに、支援者・理解者を増やしていくべく、発達障害児支援士・ライフスキルトレーナー資格など、人材育成にも尽力しています。
支援してきたご家庭は6,500以上。 発達障害児支援士は2,000人を超えました。ご家庭から支援施設まで、また初学者からベテランまで幅広く、支援に関わる方々のための教材作成や指導ノウハウをお伝えしています。
このブログでは、発達障害のあるお子様をはじめ保護者の方やご家族、支援者の方が笑顔で毎日を過ごせるよう、療育・発達支援のヒントを発信していきます。

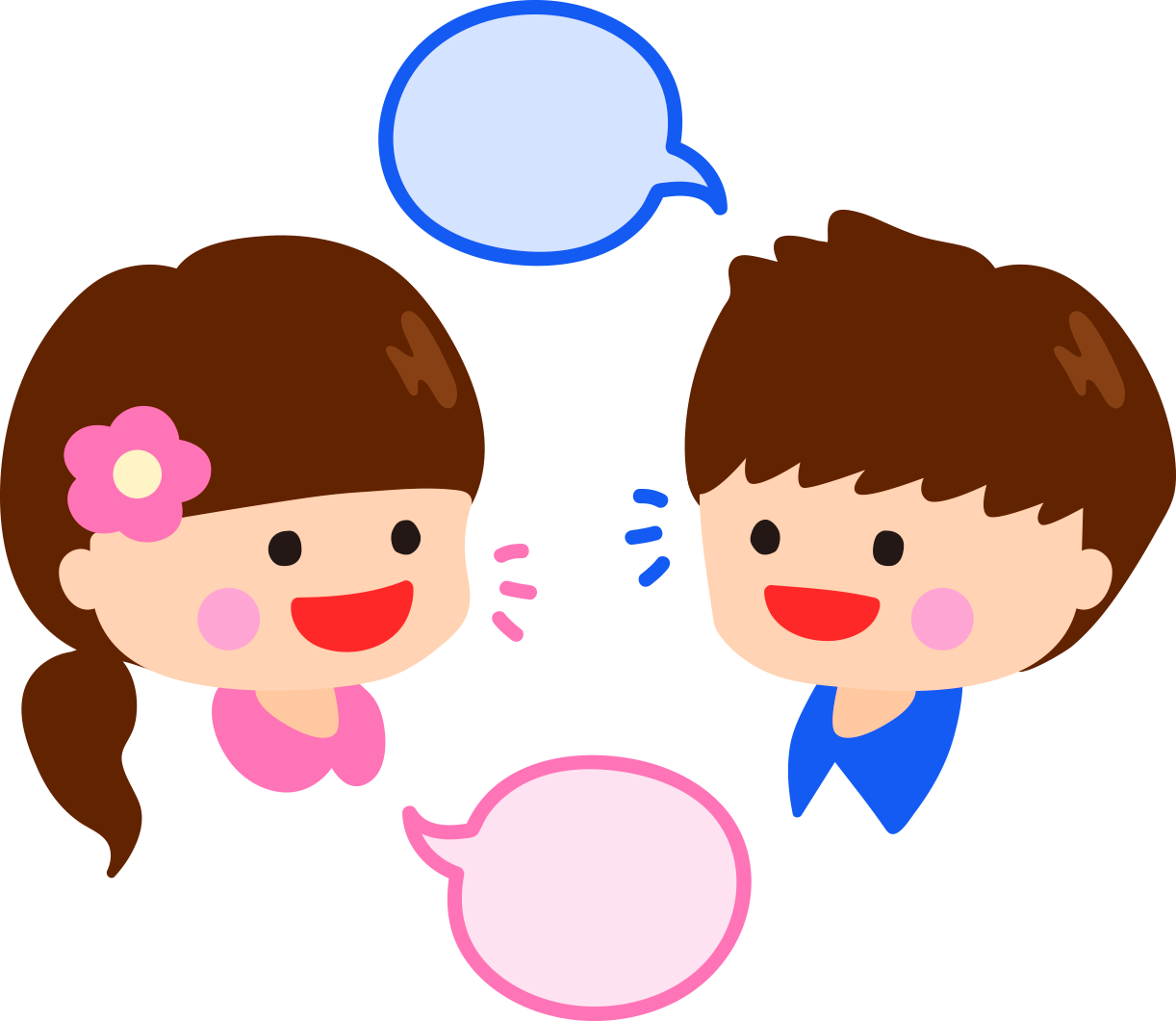
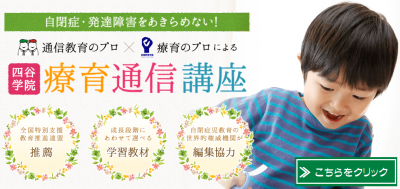

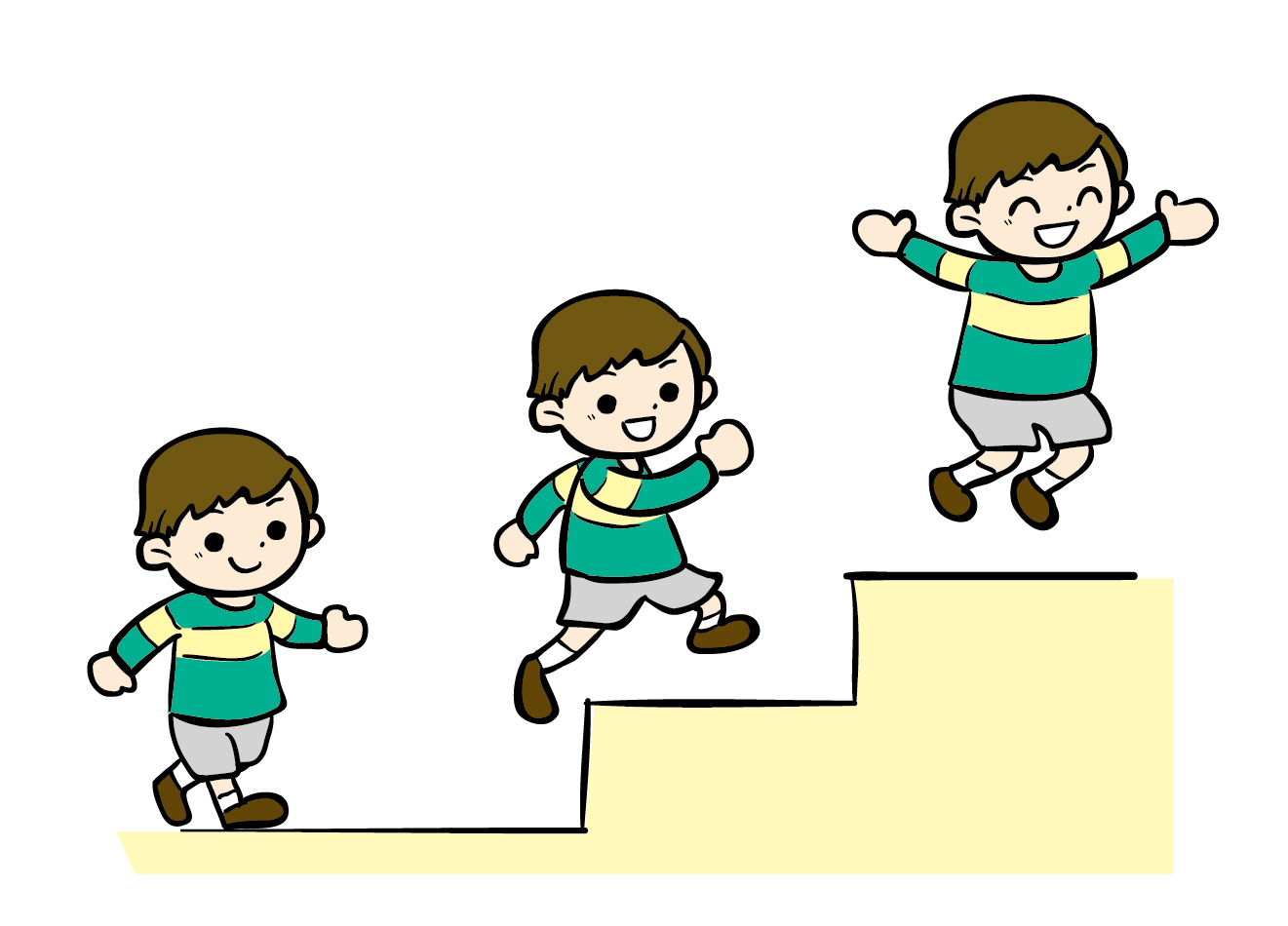
コメント